
ヨーロッパの橘歩き
三菱重工業 逸見雄人 ノルウェーの浮体橋が見れるということで、調査団に参加させていただいたが、海洋開発を中心にヨーロッパの建設技術を垣間見ることができ、大変参考になった。波穏やかなフィヨルドのNordholdland橋はほとんど揺れもなく、桁端の斬新な構造と優美な橋面の曲線が素晴らしかった。最適な自然がそこにあることが、2つの浮体橋を実現させた最大の理由なのか、風と波の過酷な条件の中で、浮体橋を建設しようと懸命に努力している彼我の違いを感じた。ノルウェーの橋梁に関する予備知識を持たずに行ったが、独自の技術を開発した新形式の浮体橋だけでなく、立派な吊橋が数多く存在しており、明石海峡大橋をはじめ長大橋技術では日本が独走していると思っていた先入観を改められた。また旅行期間中、この時期としてはノルウェーでは珍しい晴天続きで、トロルの住むという鬱蒼とした森と、澄んだ空と美しい海や湖に囲まれた北欧の生活に羨望を感じながら、冬の厳しい大自然や北海の荒波の中での石油開発の光景が思い浮かばれた。 オランダの港湾整備では、日本のように構造物で抑えつけるようなやり方ではなく、土を盛って治まるまで待つという昔ながらの工法が採られており、土の丘と近代的な風車の列に、荒波に負けずに陸地を広げていくオランダ人のしたたかさを目の当たりに見た思いがする。オランダに限らず、ヨーロッパのインフラ整備は時の流れを超越した長期的視点で行われており、構造物1つをとっても、木の文化と石の文化の違いか、見た目だけの景観設計でなく周辺の構造物を考えた重厚感のある橋造り、街造りに感心させられた。 海面下のオランダでは運河の網の中に街があるため、可動橋が数多く存在し、船が通る度に車を止めて開橋していたが、あたかも普通の交差点のようなスムーズな運営であり、交通遮断された車も待つことを厭わないようであった。 最後に駆け足で通ったパリでは、セーヌ川と橋の交じり合った景色の中、エッフェル塔の計算された構造美が素晴らしく、ギャラビ鉄道橋をはじめ橋梁技術者として成功を修めたG.エッフェルの技術の集大成である300mの塔は、できた当時は芸術家から19世紀最大の醜悪な建造物と言われながら、見事に計算された頑固なまでの技術者精神が、時代を超えた崇高感あふれるパリの顔に仕上げた感がした。短い期間ではあったが、ヨーロッパ社会に接し、伝統とゆとり溢れる生活を肌で感じ、働くことに価値観を見いだす我々との遠いを再認識し、橋や構造物の作り方だけでなく、今後の自らの生き方においても糧にしたいと思う。 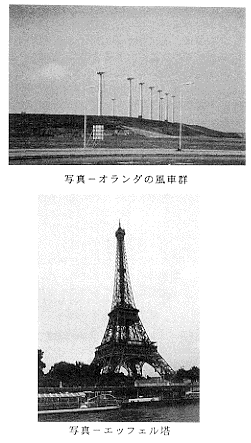
前ページ 目次へ 次ページ
|

|